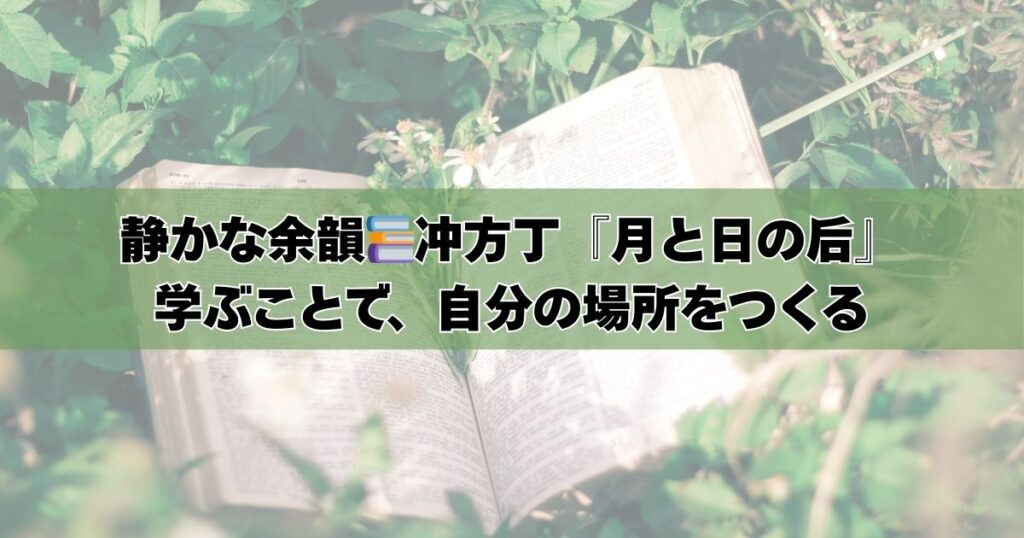
「もう女を遠ざけようとしている」
その一文に、私は物語の最初から、不穏な空気を感じて胸がざわつきました。
平安時代、女性は政(まつりごと)に直接関われない存在でありながら、摂関政治の根幹を支えてきたのもまた、女性たちでした。
しかし、都合が悪くなれば真っ先に“遠ざけられる”のもまた、女性たちなのです。
この物語の主人公・彰子は、まさにその矛盾の中で生きていた一人。
冲方丁さんの『月と日の后』は、そんな彰子の視点から描かれた、静かに熱い物語でした。
小さな后の、はじまり
物語は、彰子がまだ12歳で入内するところから始まります。
幼く、何も知らず、心も体も追いつかないまま、彼女は帝の后となる役割を与えられます。けれど、何をどうすればよいのかもわからず、ただ不安ばかりが募っていく。
そんな彼女に大きな影響を与えるのが、叔母にあたる詮子と、そしてあの『源氏物語』を生んだ紫式部です。
女に漢籍は必要ないとされた時代。
それでも、「帝を支える后であるために必要な学びがある」と気づいた彰子は、紫式部から学びはじめます。
紫式部との絆に心を打たれて
紫式部が、彰子に忠誠を誓う場面には、思わず胸が熱くなりました。
ただ命令されて仕えるのではない。心から「この方の力になりたい」と願う関係性。
それは、主従というよりも、師弟であり同志のようにも感じられました。
学ぶことで自分の頭で考え、自分の意思で歩み始めた彰子。
学問とは、本来そういう力を与えてくれるものなのだと、あらためて感じさせられました。
一条天皇との心の交わり
物語の中盤、一番心惹かれたのは、彰子と一条天皇の静かであたたかな交流です。
最初は年齢差や立場の違いに戸惑っていたふたりが、言葉を交わし、漢籍を通じて考えを共有し、徐々に信頼と愛情を育んでいく様子は、とても丁寧に描かれていて、美しいものでした。
「愛される」ではなく「支え合う」関係。
その姿に、政に翻弄される中でも自分の役割を全うしようとするふたりの強さを感じました。
後半、読めなくなった理由
正直に言うと、下巻の後半から、物語がすっと頭に入ってこなくなってしまいました。
政治的な動きが複雑になっていく中で、私が求めていたのは彰子と一条天皇の物語だったのだ、と気づきました。
とはいえ、最後の後三条天皇の善政、そして彰子の最期の場面はとても印象的で、涙がにじみました。
あれだけの困難をくぐり抜けてきた彰子が、最後に静かにこの世を去っていく──
その姿は、女として、母として、后として、ひとりの人間として本当に立派だったと思います。
「学ぶこと」への憧れ
読後、私の中に残ったのは、学びたいという気持ちでした。
知ることは、誰かのためだけでなく、自分自身を救う力にもなる。
紫式部のような先生に出会えたら、私ももっと強くなれるかもしれない。
そんなふうに思いました。
さいごに
この作品には、政治の裏側や歴史の大きなうねりも描かれていましたが、何よりも私の心に残ったのは、女たちの心の声でした。
時代が違っても、誰かに振り回されたり、役割を押しつけられたりする感覚は、どこか現代にもつながっている気がします。
自分の居場所を、自分でつくっていく。
学び、考え、愛し、闘う。
彰子のような生き方に、私は憧れずにはいられません。
最後までお読みいただき有難うございました。
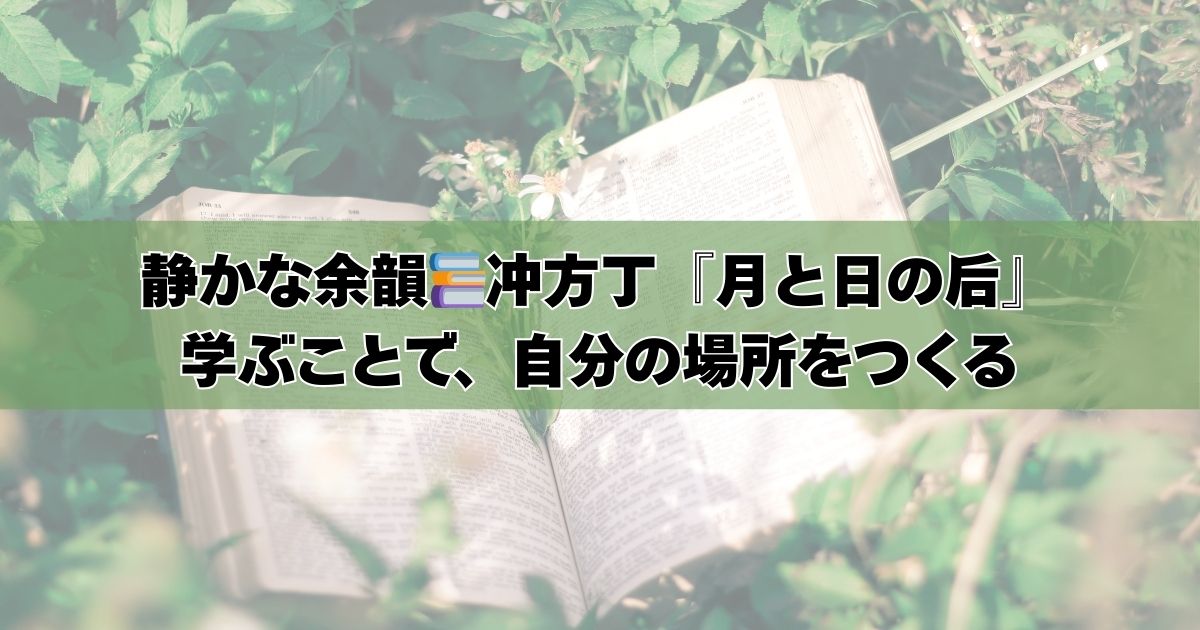
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a25cd81.77716990.4a25cd82.111b6332/?me_id=1213310&item_id=21061283&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3569%2F9784569903569_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a25cd81.77716990.4a25cd82.111b6332/?me_id=1213310&item_id=21061282&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3576%2F9784569903576_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

